システム構築
設計フェーズ – 具体的なシステム構築へ
ITインフラ基盤構築プロジェクトにおける設計書の作成プロセスを、クライアントサイドとベンダーサイドの双方の視点から解説し、各工程のポイントやテクニックを深掘りしていきます。
はじめに:ITインフラ基盤構築における「具体的なシステム構築へ」という核心
ITインフラ基盤の構築プロジェクトは、まるで壮大な建物を建てることに似ていますね。最初の段階で、どんな建物を建てたいのか(要求の明確化)を話し合い、その建物の大まかな設計図(要件定義書)を描きました。そしていよいよ、その設計図を基に、具体的な建物の骨組みや設備をどうするかという、核心のフェーズに入っていきます。それが「設計フェーズ – 具体的なシステム構築へ」というテーマです。
このフェーズは、これまでの「何をしたいか」という抽象的な要望を、「どうやって実現するか」という具体的な形にするための重要なステップです。私自身、これまで多くのプロジェクトでこのフェーズに携わってきましたが、設計の細部までこだわり、緻密に計画を立てることが、後のスムーズな構築と安定した運用に直結することを痛感しています。このシリーズが、皆さんのITインフラ基盤構築の確かな道標となることを願っています。
システム構築とは何か?設計フェーズの全体像
ITインフラ基盤構築プロジェクトにおける設計フェーズは、要件定義という航海図を手に、いよいよ具体的なシステムの姿を描き出す段階です。このフェーズでは、論理設計や物理設計といった具体的な設計書の作成を通じて、どのようなシステム構成にするのか、どのような技術要素を用いるのかといった詳細を詰めていきます。
私たちがプロジェクトを進める上で、この設計フェーズの質が、システムの性能、信頼性、そして将来の拡張性までをも左右します。後になって「この部分が想定と違う」とならないためにも、この段階でしっかりと議論し、細部まで詰めることが不可欠です。精緻な設計図がなければ、どんなに優秀な技術者がいても、意図した通りのシステムは完成しませんからね。近年はクラウドネイティブな環境での設計や、IaC(Infrastructure as Code)を見据えた設計が主流となっており、設計段階から自動化や運用効率を考慮することが求められます。このように、設計フェーズはプロジェクトの成功を左右する重要な土台作りの期間なのです。
クライアントサイドの視点:設計の方向性を承認し、未来を見据える
ITインフラ基盤構築プロジェクトにおいて、クライアントである皆様の役割は、ベンダーが作成した具体的な設計図を理解し、承認することです。この「設計フェーズ – 具体的なシステム構築へ」の段階では、ベンダーから提示される論理設計書や物理設計書の内容を吟味し、それが皆様のビジネス要件や将来の展望に合致しているかを確認することが求められます。
「専門的な内容で難しい…」そう思われる方もいらっしゃるかもしれません。ご安心ください。ベンダーは皆様に分かりやすい説明を心がけるはずです。皆様にお願いしたいのは、「この設計で、本当にやりたいことが実現できるのか」「将来的な拡張性や運用コストはどうか」といった視点で、積極的に質問を投げかけ、疑問点を解消することです。例えば、とあるお客様は、提示された設計書に記載されたストレージの構成を見て、「将来的にデータ量が倍になった場合に、この設計で対応できるのか」という鋭い質問をされました。その結果、初期投資はわずかに増えたものの、将来の拡張を見越した柔軟な設計に変更でき、長期的なコスト削減と安定稼働に繋がりました。このように、皆様のビジネスの視点から、未来を見据えた承認を行うことが非常に大切です。DevOpsの観点からも、開発と運用のシームレスな連携を意識した設計になっているかを確認することも重要です。クライアント側の視点から、設計がビジネス価値と合致しているかを見極めることが成功への鍵となります。
ベンダーサイドの視点:お客様の航海図を具体的な設計図へ落とし込む
ベンダーサイドの私たちにとって、この「設計フェーズ – 具体的なシステム構築へ」は、お客様の要件定義という航海図を、実際にシステムを構築するための具体的な設計図へと落とし込んでいくフェーズです。ここでは、論理設計と物理設計という二つの側面から、システムの骨格と細部を描いていきます。
| 設計の種類 | 目的 | 記載内容の例 |
| 論理設計 | 業務要件をITインフラの機能・データとして整理 | ネットワークのゾーン分け、サーバーの役割分担、データベースのスキーマ設計など |
| 物理設計 | 論理設計の内容を具体的なIT機器・設定として具体化 | サーバーのスペック、OS・ミドルウェアのバージョン、IPアドレス、ストレージ構成、ネットワーク機器の設定など |
この段階で特に意識するのは、「なぜその技術選定なのか」「その設計がお客様の将来にどう貢献するのか」という問いに対する明確な答えを持つことです。以前、あるシステムのリプレース案件で、お客様から「とにかく最新の技術を使いたい」という漠然とした要望がありました。しかし、具体的な要件を深く掘り下げ、運用保守の容易さやコストパフォーマンスを考慮した結果、過度に最新ではないものの、お客様のビジネスに最適な安定したアーキテクチャを提案し、ご納得いただけたことがあります。お客様の言葉の裏にある真意を汲み取り、専門家としての知見を加えて、最適な設計に繋げることが私たちの役割だと考えています。また、設計段階からセキュリティ対策を組み込む「セキュリティバイデザイン」の考え方も不可欠です。近年では、IaCを用いた自動化やGitOpsによる運用を見据え、設計の段階からCI/CDパイプラインとの連携を考慮することも重要となっています。ベンダーは、お客様の要望を具体的な技術に落とし込み、最適なソリューションを提案する役割を担います。
設計成果物の詳細:基本設計書と詳細設計書という具体的な設計図
「設計フェーズ – 具体的なシステム構築へ」における主要な成果物として、「基本設計書」と「詳細設計書」が挙げられます。これらは、システム構築の現場でエンジニアが作業を進めるための、具体的な設計図となります。
- 基本設計書:
要件定義書で定めた内容を基に、システムの全体像と主要な機能、非機能要件を具体化します。例えば、システム構成図、ネットワーク構成図(論理)、サーバーの役割、主要なデータフローなどが記載されます。クライアントとベンダーが、この設計で本当に良いのかを最終確認するための「共通の青写真」といった位置づけです。システムの骨格部分を定義するため、IaCを導入する場合は、この基本設計書に準じてコードの構造を検討することもあります。 - 詳細設計書:
基本設計書で定めた内容を、実際の構築作業ができるレベルまで詳細に記述したものです。具体的には、個々のサーバーのスペック、OSやミドルウェアのバージョン、インストール手順、IPアドレス、ストレージ構成、ネットワーク機器の設定、セキュリティ設定、監視設定などが含まれます。まさに、現場のエンジニアがこれを見ればシステムを構築できるという「究極の作業指示書」です。図表が多く用いられ、視覚的に分かりやすく記述されることが多いです。(AIが図表を直接生成することはできませんが、構成要素や関係性を言葉で詳細に記述することで、図表のイメージを伝えられます。)
これらの設計書は、ただ作成するだけでなく、関係者間で認識の齟齬がないよう、WBS(Work Breakdown Structure)を用いたスケジュール管理や、バージョン管理システムを利用したドキュメント管理を徹底し、レビューと承認を徹底することが非常に重要です。設計書は、プロジェクトを円滑に進めるための重要なドキュメントです。
品質保証とテストの観点:設計図通りかを確認する第三者の目
ITインフラ基盤構築プロジェクトにおける品質保証とテストは、これまでに作成した基本設計書や詳細設計書という設計図が、期待通りに実装されているかを確認するための「第三者の目」のようなものです。設計がどれだけ綿密でも、実際に構築されたものが設計通りであるか、そして期待通りに動作するかは、テストを通じてしか確認できません。
テストは、大きく分けて単体試験、結合試験、総合試験などのフェーズがあります。それぞれの目的は異なり、単体試験では個々のコンポーネントが設計通りに動作するか、結合試験では複数のコンポーネントが連携して動作するか、そして総合試験ではシステム全体としてお客様の要求を満たしているか、といった観点で検証を行います。テスト計画の策定やテストケースの設計は、詳細設計書の内容をベースに行われます。もし、設計書に不備があれば、どのようなテストを行えばよいのかも不明瞭になり、結果として品質が保証されないシステムになってしまう可能性があります。特に、クラウド環境では、IaCツールで自動化されたインフラ構築後のテストも重要になります。品質保証とテストは、設計の正しさを検証し、信頼性の高いシステムを構築するために不可欠です。
運用設計と継続的改善:航海の安全を確保する運用設計という監視盤
ITインフラ基盤構築は、システムが稼働して終わりではありません。むしろ、稼働後の「運用」こそが、システムの価値を最大化し、長く使い続けるための要となります。この「運用設計」もまた、要件定義という航海図から派生し、具体的なシステムの安全な稼働を保証するための「監視盤」のような重要な要素なのです。
システムが稼働した後に、どのような運用体制が必要なのか、監視はどうするのか(例:システムの状態をリアルタイムで把握するためのダッシュボードの構築)、バックアップやリカバリはどう計画するのか(例:災害時を想定した復旧手順の明確化)、インシデントが発生した際の対応フローはどうするのか(例:アラート発報から初動対応、解決までの手順書作成)、といった点を事前に検討し、設計に盛り込んでおく必要があります。これらの運用要件も、お客様のビジネスの特性やリスク許容度によって大きく異なります。例えば、24時間365日止まってはいけないシステムであれば、非常に堅牢な運用設計が求められますし、多少の停止が許容されるシステムであれば、それに合わせた設計でコストを最適化することも可能です。DevOpsの観点から見ても、運用設計を開発の初期段階から考慮することで、継続的な改善サイクルがスムーズに回るようになります。運用設計は、システムの安定稼働と継続的な価値提供を支える柱となるでしょう。
まとめ:システム構築という旅路を導く羅針盤と航海図、そして監視盤
ITインフラ基盤構築プロジェクトにおける「設計フェーズ – 具体的なシステム構築へ」というテーマ、いかがでしたでしょうか。この段階でRFPという羅針盤をしっかりと準備し、要件定義書という航海図を綿密に策定し、さらに基本設計書・詳細設計書という具体的な設計図を描き、運用設計という監視盤まで見据えられるかが、その後のプロジェクトの成否を大きく左右すると言っても過言ではありません。羅針盤と航海図、そして設計図と監視盤を正確に準備し、航海の目的地を明確にすることで、私たちはより確実に、そして安全に目標へと到達できるのです。
私自身の経験からも、この設計フェーズでの緻密な計画と関係者間の密なコミュニケーションの質が、プロジェクトの最終的な満足度に直結することを強く感じています。技術的な詳細ももちろん大切ですが、それ以上に「お客様が本当に何を求めているのか」を理解し、それを共通認識として形にしていくプロセスこそが、この設計フェーズの醍醐味なのではないでしょうか。このシリーズが、皆さんのITインフラ構築という旅の、確かな道標となることを願ってやみません。
よくある質問(FAQ)
Q1: 設計フェーズと構築フェーズの違いは?
A: 設計フェーズは「どう作るか」の計画を練る工程であり、構築フェーズは実際にシステムを構築・実装する工程です。
Q2: 基本設計と詳細設計の使い分けは?
A: 基本設計はシステム全体像を示す上流設計、詳細設計は構築作業の具体的指示書として機能します。
ITインフラ基盤構築 設計書シリーズ



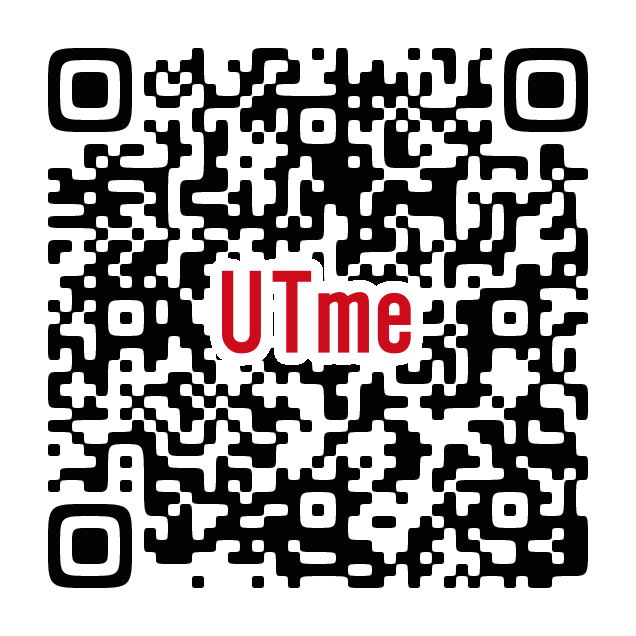
コメントを残す